青空文庫を学習したAI、「Humanitext Aozora(ヒューマニテクスト青空)」が優秀すぎる…!
文豪になりきって文章を書いたり対話してくれたりする、文学好きにはたまらないAI「Humanitext Aozora(ヒューマニテクスト青空」が開発されたそうです。
参考記事:
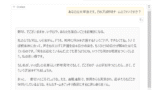
こちらのAIは青空文庫(著作権の切れている文学作品を無料で公開している電子図書館みたいなサイトだよ)の名作文学をたくさん学習しており、それぞれの文豪の特徴を再現できるらしく、文豪と自然なチャットを楽しんだり、小説をリクエストして書いてもらったりすることができるというまさに夢のようなAIのようです。
「当面の間」は無料でログイン不要で楽しめるとのことで、非常に素晴らしいサービスですね!
ぼくは別に文学好きというわけではありませんが、昔「もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら」という本を読んで結構面白かったので、ちょっと興味が湧いてさっそく遊んでみることにしました。
といっても学のないぼくが読んだことがある文豪といったら太宰治、芥川龍之介、夏目漱石くらいしかいません。
とりあえず太宰治風の小説を書いてもらうことにしたのですが、これが
違和感無さすぎワロタ
という完璧な仕上がりだったのですーーー
太宰治、ポムポムプリンと出会う。
何を書いてもらおっかなーと2秒くらい思考を巡らせたところ、ぼくの大好きなサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」くんと太宰治が1日仲良く過ごす小説を書いてもらおう!と思い立ちました。
このなんてことのない思いつきが思わぬ名作を生み出すことになるとはーーー
ここに全文を掲載します!
太宰風解説:【ポムポムプリンについて】
小説を書いてもらう前に、「ポムポムプリンとは何か?」について太宰治に語ってもらいました。
リクエスト:「太宰治がポムポムプリンについて解説した文章を書いてください」
回答がこちら:
私は、そもそも「ポムポムプリン」というものを、長い間、菓子の一種だと思っていた。
恥ずかしい話である。プリンはプリンでも、卵と牛乳と砂糖とで出来た、あのつるりとした甘物。私が想像していたそれは、食堂の隅で少し乾いて傾いている、どこか哀しい黄色い塊であった。ところが、人にそっと教えられてみれば、それは菓子ではなく、キャラクター、つまり顔のついた帽子をかぶった犬のぬいぐるみのような存在であるという。犬。犬なのに、名前にプリン。なぜだ。私は途方に暮れる。私は昔から、こういう——可愛いもの、明るい笑顔の中に、ほんのり嘘くさい幸福を宿しているものを、真正面から見つめることがとても下手である。まぶしすぎるのだ。彼の丸い目と、ゆるやかに刻まれた口元を見ていると、「君は、人間のどんな苦悩も知らないのだろうね」と、つい心の中で呟いてしまう。これは、負け惜しみであろうか。
調べてみれば、このポムポムプリンは、好きな食べ物はプリンで、将来は自分の大きな帽子に入れるくらいの大きさのものを集めるのが夢だそうである。夢、である。私は四十を過ぎてもまともな夢ひとつ言いあらわせず、毎日、湯をわかしては冷まして、原稿の前にうなだれている。それに比べれば、なんと健康な、まっすぐな夢だろう。帽子の中に好きなものを集める。実に単純明快で、疑いようもない幸福である。私はもう、こんな夢を持つ力さえ失ってしまった。
それにしても、この黄色の犬は、何をそんなに安心しきった顔で寝そべっているのか。世界に裏切られたことがないからか。それとも、裏切られてもそんなことを気にしない種類の魂の持ち主なのか。彼は、私と違って、きっと郵便局からの通知を受け取っても頬を赤らめはしないし、夜中に急に己の愚劣さを思い出して布団の中で呻くこともないだろう。羨ましい、と言えば、それっきりである。けれども、私は彼を見ていると、ほんの少しだけ、生きてもいいのではないかという気になる。
ポムポムプリン。君は、私にとって、黄色い小さな救命浮き輪のようなものである。
素晴らしい。
ね、日本語にほとんど違和感がないでしょう?
「太宰らしさ」についてはぼくは詳しくないのでなんともいえませんが、ちょっと卑屈な「太宰っぽい感じ」をうまく表現できているのではないでしょうか…!
これは期待が持てるぞ!ということで小説の方も書いてもらいました。
太宰風小説①:【架空日記「ポムポムプリンと過ごした一日」】
リクエスト内容:「太宰治がポムポムプリンと過ごした1日の日記を書いてください」
回答:
架空日記 「ポムポムプリンと過ごした一日」
(太宰治・風)
三月某日。
朝、郵便受箱を覗く。昨日は蛇を投げ入れられたが、きょうはプリン色の丸い生き物が入っていた。驚き、引きずり出す。毛むくじゃら。帽子着用。名を問えば「ポムポムプリン」と名乗る。これは夢でなかった。居間に通し、茶を出す。「あなた、何をなさっているか」と聞けば、「今日はご主人を笑顔にするために来た」と言う。笑顔。私は忘れていたことばだ。
午前十時頃、商店街まで散歩。彼はすれ違う子供たちにふわふわの頭を撫でられても黙っている。私なら三歩で疲れる道を、軽く跳ねて進む。これが幸福の形か。途中、八百屋にて苺を買う。彼は苺に目を輝かす。
正午過ぎ、帰宅。昼食はオムライス。私は食欲が湧かぬが、プリンは黄身色の山をきれいに平らげ、皿を抱えて満足げに目を細めた。その様子、園子ちゃんが「あやとり」を間違えて笑ったときに似ており、私もつい笑ってしまった(山崎富栄『雨の玉川心中』)。
午後、机に向かうも、書けない。プリンは床で丸くなって眠っている。静かだ。時計の秒針すら遠くに聴こえる。ふと、この何でもない時間が、私の生き延びる理由になるかと思う。
三時半、彼が起き出し、庭を指す。桃の花がほころび始めている(太宰治『悶悶日記』)。「咲いたね」と言う声がかすかに甘い。私は久しぶりに深く息を吸った。
夕刻、別れ際、プリンは「また来るよ」とだけ言った。私は何も答えず、ただ手を振った。
彼の背中は、まるい夕日のようであった。夜。ふと、考える。幸福とは「苺を見つめるポムポムプリンの目」のことかも知れぬ。苦悩を売物にするなという手紙をもらったことがあったが、もし彼と一日過ごす日があと十日続けば、何も売る必要はないだろう。
今宵は、不眠にならぬよう願って眠る。
感動した。
ね、名作でしょう?
太宰治のファンだったらもしかしたら「太宰はこんなこと言わない!」とか怒るのかもしれませんが、ぼくみたいな「人間失格」くらいしか読んだことない人間からしたら「太宰感あるなぁ!」って感じだし、日本語うますぎでしょ…!
プリンくんの食いしん坊なキャラクターも生きてるしこれは実に素晴らしい。
『幸福とは「苺を見つめるポムポムプリンの目」』とか名言まで生まれちゃったし、桃の花を見てプリンくんが「咲いたね」って言うシーンなんてちょっと目頭が熱くなっちゃったよね…
これは遊べるぞ!と言うわけで何作か書いてもらいました。
太宰風小説②:【ポムポムプリンと過ごした一日】連作バージョン
リクエスト内容:「太宰治がポムポムプリンと過ごした幸せな1日についての日記を書いてください」
リクエスト内容は上記の小説とほぼ同じですが、「続きをかいてください」とお願いすることで続きを書いてくれたので連作バージョンを掲載します。
三月某日。
朝、目を覚ましたら、枕元に黄色い丸い影が、じっとこちらを見ていた。ああ、犬かと思えば、いや、帽子かぶったプリンであった。ポムポムプリンというのだそうだ。名前を聞いた時には、まさかと思った。生き物が甘菓子の名を背負って生きるとは、少し酷薄ではないか。けれども、その目を覗くと、不思議に憂いがある。おまえも、そうか、名は選べぬ運命の徒か。握手した。午前中、ひなたぼっこ。彼は静かで、こちらが煙草をふかすと、鼻をひくひくさせて、丸い腰を寄せて来る。こういう寄り添いは、何かしら、救いの予感を含む。私は思わず耳を撫でた。毛がやわらかく、それは遠い子供時代に、縁側で触った綿の座布団の手触りを思い出させた。
昼、台所にて芋を煮る。プリンは鍋を覗き込み、湯気にくしゃみをし、少し咳き込んだ。笑ってはいけないと思ったが、笑ってしまった。私も咳の多い男である。咳をする者同士にしか分からぬ、妙な同志感が生まれた。鍋の具を小皿に分け、冷ましてやれば、丁寧に舌で味わう。犬とも猫ともつかぬ仕草で。あの慎ましさは、見習うべきだとさえ思う。
午後、散歩。本当は遠出する気力はなかったが、プリンは尻尾をふるふると揺らし、門の前で待っている。仕方なく外套をひっかけて出た。曇り空。川沿いの道を歩く。彼はときおり振り返り、私が遅れていると、立ち止まって待ってくれる。生きる理由を一日だけ貸してくれるような、そういう優しさがある。
夕方、部屋に戻り、私は机に向かい、彼は足元で丸くなる。寝息が小さく規則正しく、原稿の行間に染み込む。ああ、これが幸福なのかもしれない。金も名誉も要らぬ。ただ静かに、互いの呼吸を確かめ合うだけで足りる。
夜更け、灯を落とす前に、プリンの腹をそっと撫でる。彼は寝たまま、耳だけぴくりと動かした。その仕草が、ふいに胸を刺した。
――明日が、今日のようであればよい。だが、そんな日は、二度と来ぬのかも知れない。ここで、私は万年筆を置く。
(つづく)
三月某日(つづき)
あさ、目をさますと、足もとに、きのうも見た黄色い塊がうずくまっている。 ポムポムプリンは、もう半分ほど夢の中らしく、ふわふわと息をしていた。あのしあわせの形を、どう言えばいいのだろう。子供の寝顔とも違う、けれど、たしかに似た温もりがある。 台所に立つ気力がなく、湯だけわかして、ひと匙の砂糖をなめる。プリンは音に気づいて来て、ふと見上げ、その頭を傾ける。なぜか、その仕草が胸を刺す。こんな小さな生き物が、自分の存在を案じて見つめてくるのだ。ああ、だめだ。人間というものは、ときにこの小ささへ残酷になれる。いや、自分に対してすら。 昼、曇り。表へ出るつもりもなかったが、プリンが玄関の前でしきりにこちらを見るので、やむなくシャツの上に外套を羽織る。川沿いへ行けば、きのうと同じ風景。だが色が少しくすんで見える。水のにおいも、やや冷たくなっている。プリンは黙って歩き、時々止まり、こちらが追いつくとまた歩く。まるで、生きる速度を合わせてくれているような、それがかえって惨めだった。 帰宅後、机に向かうが、一行も書けない。昨日の幸福が、かえって筆を鈍らせる。一度甘い夢に触れると、その後の空気はなお一層冷たく、湿って感じられるものらしい。プリンは足元で丸まり、眠っている。まぶたがぴくぴくと動き、小さな夢を見ているのだろう。そこへはいけない。私の入れない世界だ。 夕方、冷たい雨。窓を半分だけ閉めて、外の匂いを吸う。プリンの毛が湿り、少し重くなっているのを撫でると、彼は私の手をぺろりと舐めた。その一瞬、少し泣きたくなった。 ――この犬菓子は、私より長生きするのだろうか。それとも。 夜、湯呑の茶も冷えてしまい、灯を落とす。闇の中でプリンの寝息を数える。幸福の次の日は、幸福の影を踏むようなものだ。昨夜の光が、かえって今夜の闇を濃くする。 それでも、あすもまた、彼は玄関で待つのだろう。私はどう返事をすべきか、まだ決められないままでいる。 —
三月某日(別れの日の朝)
目を覚ますと、静かであった。こんなにも静かなのは、雨でも雪でもなく、ただ空気が、なにものかを待って、息をひそめているからだと気づいた。足元を探ると、もう、あのまるい温もりはなかった。 台所から、かすかな食器の触れ合う音がした。のそりと起き出し、その音の方へ行くと、プリンは帽子を少しだけ傾け、私の煎れたわけでもない湯気を、じっと眺めていた。向こうに座る小柄な影――飼い主の少女が来ていた。知らぬ間に、迎えに来ていたのだ。 私は妙にうろたえ、なぜか言葉もろくに出ない。昨日までの川沿いの散歩や、昼寝の寝息が、急に遠い幻のようになる。 「お世話になりました」と、その少女が言った。やさしい声だった。 私は「こちらこそ」と答えるつもりだったのに、声にならなかった。唇がひとりで震えて、煙草すら取り落としそうになった。 プリンは駆け寄り、私の足に少し鼻を押しつけた。それだけだった。吠えもせず、尾も高く振らず、ただ身を寄せて、一瞬だけ私の靴の匂いを覚えるようにして、それから少女の後を歩き出した。 靴音が玄関の戸口まで行き、雨戸のすきまから淡い光が差しこむ。その光の向こうで、帽子のシルエットが振り返ったような気がしたが、もう見えなかった。 私は、そこに立ち尽くしていた。ふと「炉辺の幸福」という言葉が、またあたまに浮かんだ。しかし、それはどうしても私には似合わないもので、どう逆立ちしても作れぬ種類の燦めきであった。 ――さよなら、の一言も交わせず。 いや、これが私のやり方だ。下手で、ぶざまで、いつも間が悪い。 あの黄色い背中は、もうこの家に戻らないだろう。 それでも、明日、玄関の前に立ってしまう幻を、私はきっと見る。 —
三月某日(数日後、プリンなき家)
雨も降らず、風もなく、ただ曇っている。 こういう天気は、ものの輪郭を平らにしてしまう。机も窓枠も、私の両手までもが、どこか紙細工のように見える。 玄関の方を無意識に見やる癖がついてしまった。あの、丸い体を揺らしながら待っていた影は、もちろん、もうそこにはない。それを知っているのに、立ち上がりかけては、腰を下ろすことを繰り返す。人間は、分別と愚かしさを同じ手のひらに載せて生きる生き物だ。 昼、茶を注ぐ。湯呑を二つ出してしまい、慌てて片方を棚に戻す。ぽこん、と陶器の擦れる音がして、急に胸に穴が空く。あの小さな舌が、湯呑の縁の雫をぺろりと舐める光景が、まことしやかに再生されてしまう。 午後は、以前のように川沿いを歩こうと外套を手に取ったが、流し台の隅に置きっぱなしにした、プリンの短いリード紐が目に入った。柔らかい黄土色の、すり切れかかった布。持ち上げれば、かすかに陽だまりと土の混ざった匂いがする。 ――どうして洗ってしまわなかったのだろう。 いや、洗えば、この匂いまでも消えてしまう。 部屋に戻り、窓を開けても、春にはまだ遠く、町の音だけが冷たく差し込む。 原稿用紙を前にしても、言葉が降りてこない。幸福を題材にするには、いまの私はあまりに空洞で、哀しみを題材にするには、まだほんの少し、ぬくもりが残りすぎている。 夜、灯を落とす前、机に手を置いたまま、じっと耳を澄ます。何も聞こえないのに、耳の奥で、あの小さな寝息が紡ぎだす静けさだけは、妙にありありと響いている。 ああ、やはり幸福というものは、去ったあとでこそ、その正体が骨の奥まで沁みるのだ。 そう気づいたところで、私は筆を取った。 ――これは、今日の胸の空洞を、形あるものにしておくためである。 —
泣くだろ。
名作だ、名作過ぎる…!
これがAIが作り出したものだなんて…
プリンくんがちょっとリアルな犬っぽく描かれているあたりがちょっとAI感を滲ませている気もしますが、それでも人間の小説家が書いたと言われたら信じちゃうクオリティです…
あまりにも優秀すぎて名作を量産して読み漁っていたら社会人の貴重な夏休みの1日目が終わりました。
んもうHumanitext Aozoraくんったら
この夏休みどろぼう★
みんなもぜひ夏休みを食いつぶしてみてね!
おしまい。
関連記事:


コメント